-
 2021/11/02高齢者鍼灸ゼミ
2021/11/02高齢者鍼灸ゼミ- 高齢者鍼灸ゼミに行ってきました!~ひざへの刺鍼と吸い玉(カッピング)~
-
日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本日は、4大鍼灸ゼミの1つ、高齢者鍼灸ゼミの実技授業を見学してきました! 講師は鍼灸学科専任教員、山中先生です♪ 今日はひざの痛みに効果的な施術を行っていきます。 生徒の前で刺鍼のお手本を見せる際、「赤い鍼と青い鍼、どっちが写真映えする~?」と気を配って下さる山中先生!笑 ひざの痛み 血海(けっかい)・梁丘(りゅうきゅう)・鶴頂(かくちょう)・両膝眼・内側外側関節裂隙を刺鍼していきます! 初めて見ると読めないツボばかりだと思いますが、授業でしっかり学ぶので安心してくださいね。 それぞれのツボに由来があって面白いので、興味があれば是非調べてみてください♪ 山中先生のお手本を見た後、生徒同士で刺鍼し合います。 患者さん役の年齢設定を決めたり、施術に入る前の患者さんとのコミュニケーションもしっかりと行っていきます。 生徒の皆さんが義務ではなく、本当に楽しそうに患者さん役の人とコミュニケーションをとっているので、実際の現場での活躍が今からとても楽しみです♪ ひざへの吸い玉(カッピング) これまでのゼミでも何回か行ってきた吸い玉ですが、今日はいつもの背中ではなく、ヒザへ行います! 背中よりも難易度が高く、落として割ってしまう生徒もいるとか…! 思わず「上手!」と声が挙がるほど、皆さん吸い玉をマスターしていました! いつもの練習の賜物ですねっ。 これからも楽しく、集中して練習していきましょう☆ 鍼灸学科ブログでは、授業やゼミの様子やコラムを掲載しております >ほかの鍼灸学科ブログはこちら オープンキャンパスでは実際に鍼や吸い玉に触れることができます♪ >オープンキャンパスの予約はこちらから まずは日本医専を知ろう! >資料請求はこちら]
-
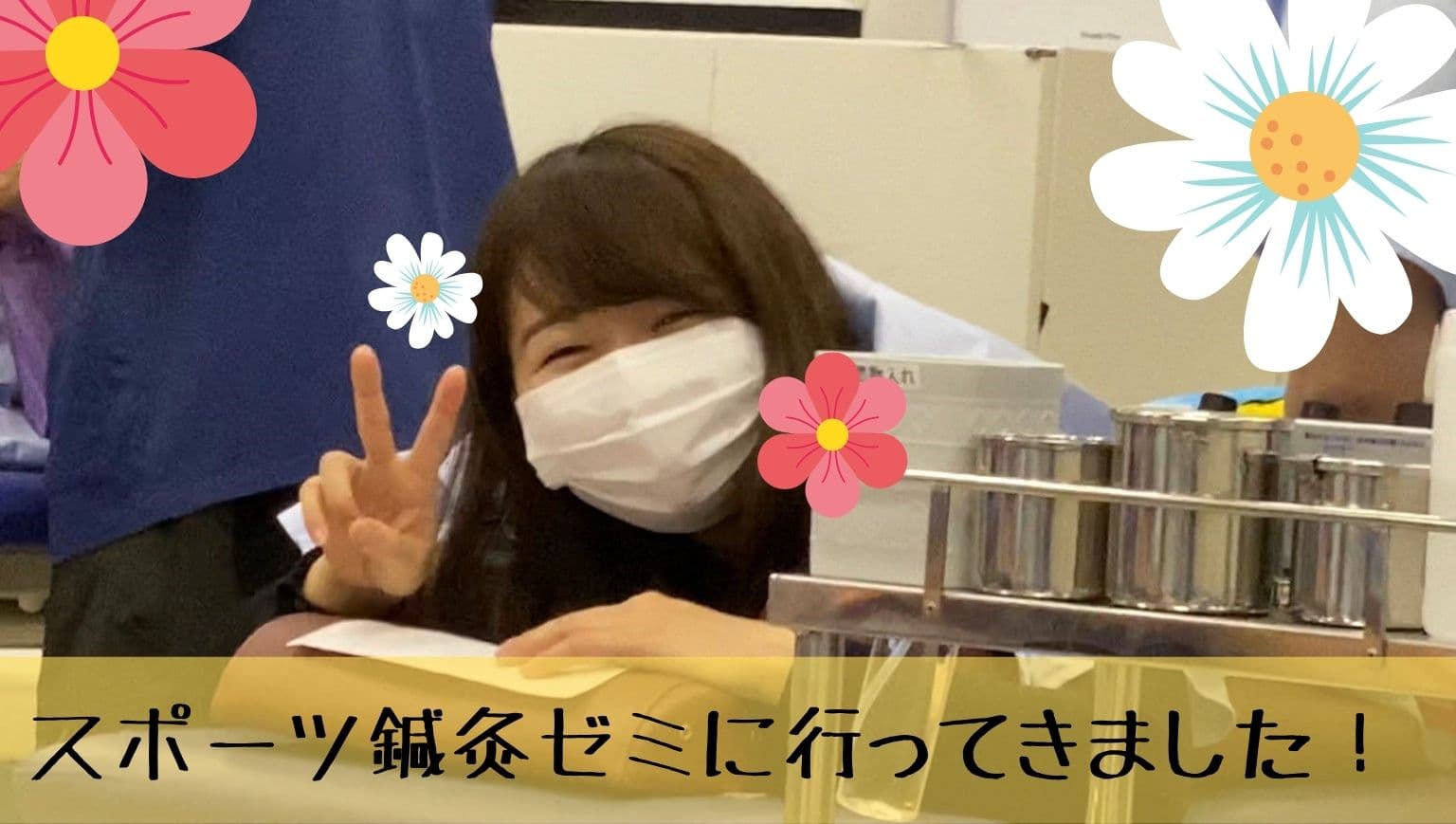 2021/10/28スポーツ鍼灸ゼミ
2021/10/28スポーツ鍼灸ゼミ- スポーツ鍼灸ゼミに行ってきました ~脚の可動域をひろげる!~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 4大鍼灸ゼミの1つ、「スポーツ鍼灸ゼミ」の見学に行ってきました! 担当は本校の鍼灸学科専任教員で現役のスポーツトレーナー、大島先生です! 今日のメインテーマは「仙腸関節機能障害と鍼灸治療」です! 仙腸関節機能障害(せんちょうかんせつきのうしょうがい)の症状としては、 ———この痛みは長時間の立位や座位により出現し、時には大髄部、殿部、鼡径部などの関連痛を生じる。横になっていると痛みは消失する——— 上記は大島先生の授業のプリントから抜粋しましたが、なんだかとっても難しそう…! 刺鍼も難しいそうで、「ちょっと今日のは難しいけど、しっかり説明するからね!イメージが出来ないと鍼もあたらないから!」と大島先生。 生徒たちも、実技で刺鍼する前にしっかりイメージしようと真剣な表情です。 今回の施術では、脚の可動域が上がるだけでなく、腰の痛みを抱えている人にも有効なので、下半身を酷使するスポーツ選手にとってとても効果的です。 スポーツ鍼灸ゼミでしっかり覚えていきましょう! 施術前に、患者役の生徒は可動域の効果を確認する為、脚の上げ下げを行います。 経穴を探り、刺鍼した後は低周波鍼通電療法(パルス)で電気を流します。 教室から「全然あたらない…」「どこ…?」と苦戦している様子がありました…。 生徒1人1人に対し、大島先生が丁寧に解説していきます。 難しい内容も、大島先生が「難しいよな…ドンマイだ…ドンマイケルだな…ここだ…ここに刺すんだ…デュクシ!」と面白い擬音で説明してくれるので、教室は笑顔であふれています! 効果を実感して、脚を上げ下げしながら喜ぶ場面も♪ 難しい内容に取り組みながら、熱心に、そして笑顔で頑張る生徒たち。 この笑顔で、将来の患者さんにより良い施術を行ってくださいね☆ 取材をしていて、みんなの将来がとても楽しみになりました! ありがとうございました! 鍼灸学科ブログでは、授業やゼミの様子やコラムを掲載しております >ほかの鍼灸学科ブログはこちら オープンキャンパスでは実際に鍼や吸い玉に触れることができます♪ >オープンキャンパスの予約はこちらから まずは日本医専を知ろう! >資料請求はこちら]
-
 2021/10/26高齢者鍼灸ゼミ
2021/10/26高齢者鍼灸ゼミ- 高齢者鍼灸ゼミに行ってきました! ~フレイル対策・ごえん予防・吸い玉療法(カッピング)~
-
日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本日は、4大鍼灸ゼミの1つ、高齢者鍼灸ゼミの実技授業を見学してきました! 講師は鍼灸学科専任教員のいつもニコニコ、山中先生です♪ ~フレイル対策・誤嚥予防~ フレイルとは、日本老年医学会が2014年に提唱した概念で「Frailty(虚弱)」の日本語訳です。 適切な治療や予防を行うことにより、要介護状態へ進まずに済む可能性を秘めている状態のことを指します。 誤嚥(ごえん)は皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか? 飲食物が器官に入ってしまうことで、高齢者の食事の場合は特に注意が必要です。 このフレイルと誤嚥の対策で共通したツボの足三里(あしさんり)と太谿(たいけい)をさしていきます! 実際に高齢者の方へ施術する意識を持つために、患者さん役の年齢設定をするのですが、ご近所付き合いや孫の名前などもみんな細かく設定するので、施術前から盛り上がります笑 いざ施術する時は集中した表情…頼もしいです…!! 高齢者の方々は皮膚感覚が麻痺し、自分の痛みを申告できない場合もあるので、より施術の正しさが求められます。 表情をよく見て変化を読み取り、細かい声かけを行っていきましょう! ~吸い玉療法(カッピング)~ 授業の後半は吸い玉です! 吸い玉で期待できる効果として「血行を良くする」「血液をきれいにする」「皮膚の若さを保つ」「関節の動きを円滑にする」「神経を正常に調整する」「内臓諸機関を活発にする」などがあります。 鍼ではなく、この吸い玉だけを希望される患者さんもいらっしゃるそうですよ! 吸い玉で使う道具は、オープンキャンパスでも取り扱っているので、見たことがある人もいるのではないでしょうか♪ 何回か吸い玉はゼミの中で行っているのですが、今日初めて挑戦する生徒がいたので、山中先生がしっかり説明します。 練習を重ね、皆さん少しずつ感覚を掴んでいっている様子でした♪ 今までは背中への吸い玉でしたが、次回はヒザへ吸い玉をしていきます! 楽しく、そして集中しながら頑張りましょう! 皆さんの頑張りが、未来の患者さんの笑顔に繋がっていきますよー! 鍼灸学科ブログでは、授業やゼミの様子やコラムを掲載しております >ほかの鍼灸学科ブログはこちら オープンキャンパスでは実際に鍼や吸い玉に触れることができます♪ >オープンキャンパスの予約はこちらから まずは日本医専を知ろう! >資料請求はこちら]
-
 2021/10/21スポーツ鍼灸ゼミ
2021/10/21スポーツ鍼灸ゼミ- スポーツ鍼灸ゼミに行ってきました ~大殿筋をぷすっと!~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 4大鍼灸ゼミの1つ、「スポーツ鍼灸ゼミ」の見学に行ってきました! 今日は「大殿筋(だいでんきん)」というお尻の筋肉に刺鍼していきます! 立つ・座わる・歩く・階段昇降など日常生活動作のほか、走る・ジャンプといった動作時にも働く、とても重要な筋肉です。 担当の大島先生の説明を真剣に聞く生徒たち…! さまざまな動きに関係する筋肉のため、アスリートやスポーツをしている方のパフォーマンスに大きく影響するので、スポーツ鍼灸ゼミでしっかり学んでいきましょう! 大島先生は「こうしたらダメ」という言葉を使わず、「こうしたらドンマイだね!」と生徒に声をかけます。 小さな違いですが、こういう言葉の気遣って素敵ですよね♪ 生徒たちもリラックスした様子で刺鍼し合います。 余談ですが、各自が使用するタオルに個性が出ていて素敵だな~といつも思っています笑 「痛くない?」など、お互いに声を掛け合いながら実技授業が進みます。 実技授業の終わりには、「難しいと思いますが、練習を重ねてスタンダードに出来るように頑張りましょう!」と大島先生。 その生徒の頑張りに応える大島先生の姿と、生徒たちの一生懸命な姿勢が印象的でした♪ 次回のゼミも頑張ってくださいね! 鍼灸学科ブログでは、授業やゼミの様子やコラムを掲載しております >ほかの鍼灸学科ブログはこちら オープンキャンパスでは実際に鍼や吸い玉に触れることができます♪ >オープンキャンパスの予約はこちらから まずは日本医専を知ろう! >資料請求はこちら]
-
 2021/10/20高齢者鍼灸ゼミ
2021/10/20高齢者鍼灸ゼミ- 高齢者鍼灸ゼミに行ってきました! ~腰痛と転倒防止対策~
-
みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本日は、4大鍼灸ゼミの1つ、高齢者鍼灸ゼミの実技授業を見学してきました! 講師は鍼灸学科専任教員の山中先生です。 わかりやすく、そして楽しく授業を進めてくれる人気の先生です♪ ~腰痛対策および転倒防止の施術~ まずは腰痛についての説明! どんな原因で腰痛が起こるのかを「経脈の損傷」「気血運行不利」「痹証」「老年・久病・房事過多」の4種類に分けて解説します。 ゼミに参加したみなさんはこれがなんだかわかりますよね? そして実際に山中先生が診た患者様の中で多かった症例も紹介していきます。 今回は「寒さによる腰の痛み」と「ひざの痛みやだるさを伴う腰の痛み」を紹介! 学生のみなさんは真剣に山中先生の解説を聞き、メモを取っていました♪ 後半はお待ちかねの実技の時間です! 今回は「足臨泣」というツボを刺激し、股関節の動かすことで可動域を調整して腰痛対策や転倒防止につながる施術法を学びました。 まず最初に股関節の可動域をチェックし、左右で動きが悪い方の足臨泣に鍼を打っていきます。 そのまま股関節をゆっくりと屈伸運動させていきます。 鍼を刺すだけでも可動域は広がるそうですが、この屈伸運動をすることでより早く効果が出るそうです! 足臨泣の施術が終わったら、次は腰への吸い玉(カッピング)です。 前回のゼミでも腰への吸い玉を学びましたが、今回は「座ったままでの吸い玉」です!! ≪前回の高齢者鍼灸ゼミの様子はこちら≫ 山中先生がまず見本を見せながら施術する際の注意点やコツを解説していきます。 そして学生さんたちも実際にやっていきますが、なかなか難しそう…! 先生に丁寧に教えてもらいながら、全員つけることができました♪ どんどん練習して、上達していきましょう! そして、たくさんの患者さんを笑顔にしてくださいね♪ 鍼灸学科ブログでは、授業やゼミの様子やコラムを掲載しております >ほかの鍼灸学科ブログはこちら オープンキャンパスでは実際に鍼や吸い玉に触れることができます♪ >オープンキャンパスの予約はこちらから まずは日本医専を知ろう! >資料請求はこちら]
-
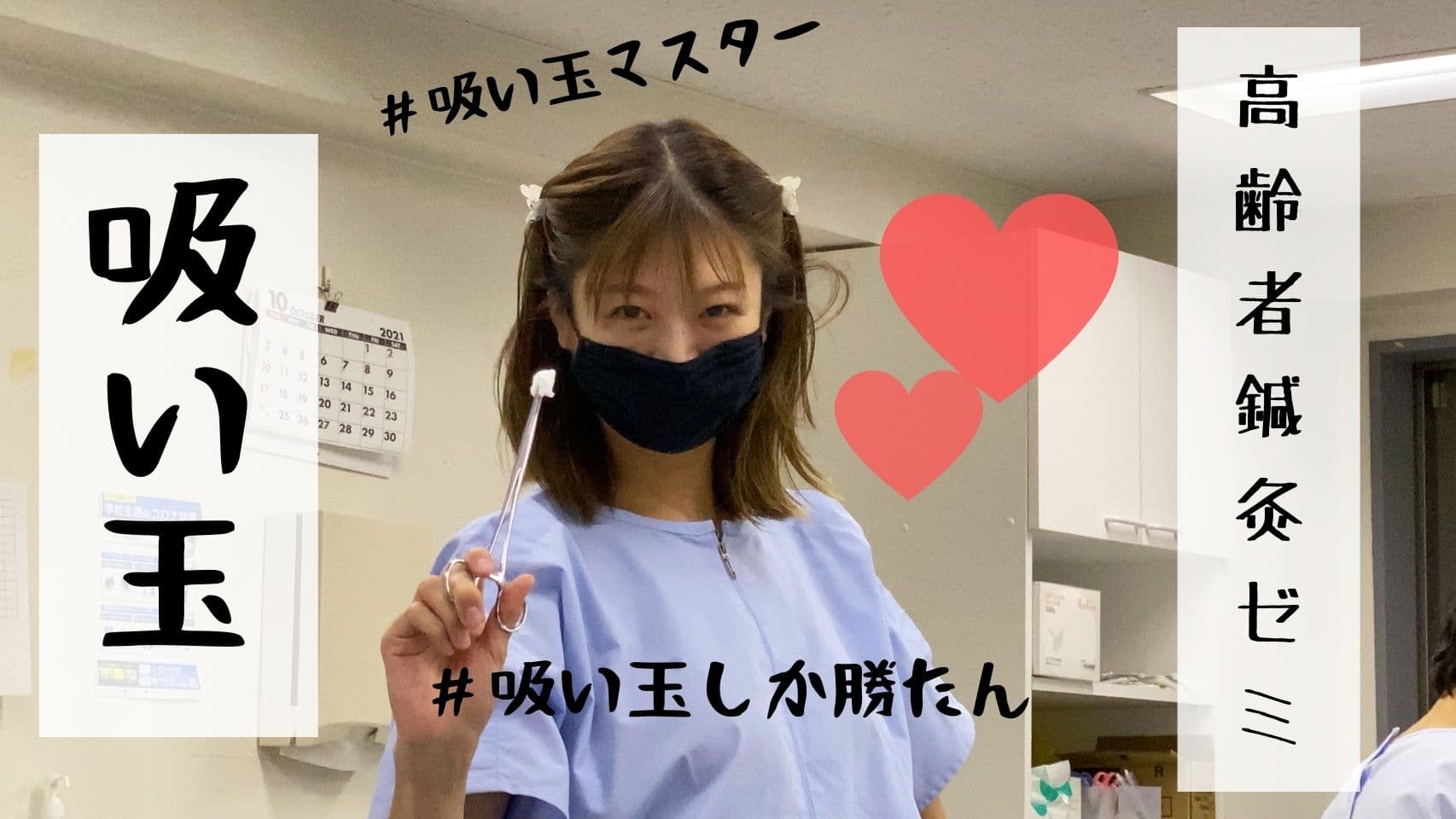 2021/10/14高齢者鍼灸ゼミ
2021/10/14高齢者鍼灸ゼミ- 高齢者鍼灸ゼミに行ってきました! ~吸い玉療法(カッピング)~
-
みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本日は、4大鍼灸ゼミの1つ、高齢者鍼灸ゼミの実技授業を見学してきました! 講師は鍼灸学科専任教員の山中先生です。 なんだか、どなたが先生なのかわからない写真ですが…笑 ダブルピースをされている方が、山中先生です! わかりやすく、そして楽しく授業を進めてくださるので、教室はいつも笑顔でいっぱい♪ ~吸い玉療法(カッピング)~ 吸い玉で期待できる効果として、血行を良くする、血液をきれいにする、皮膚の若さを保つ、関節の動きを円滑にする、神経を正常に調整する、内臓諸機関を活発にする、などがあります。 鍼ではなく、この吸い玉だけを希望される患者さんもいらっしゃるそうですよ! 吸い玉で使う道具は、オープンキャンパスでも取り扱っているので、見たことがある人もいるのではないでしょうか♪ 授業でもしっかりと丁寧に扱い方や注意点を伝えていきます。 実技授業は知識だけでなく、手や指の感覚が大切です。 生徒一人ひとりにその感覚を伝えるために、手を取って丁寧に伝えていきます。 吸い玉は施術を失敗してしまうと、火傷を負ってしまったり、皮膚が避ける可能性もあります。 患者さんの症状や健康状態によっては施術を避けて別の施術を提案することも大切です。 山中先生が実際に施術した患者さんとの体験談も交えながら、実技授業が進んでいきます。 「山中先生と僕が施術した吸い玉、全然違います!」と生徒が報告してくれる場面も。 確かに左右で全然違いますね! たくさん練習して、山中先生の技術に近づいていきましょう! そして、この素敵な笑顔で患者さんを施術してくださいねっ♪ >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら >>オープンキャンパスの予約はこちらから >>資料請求はこちら]
-
 2021/10/12その他
2021/10/12その他- 【コラム】「マスク肌荒れ」を防ぐには
-
こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校です。 毎日のマスク生活は肌への負担も増えてしまっているせいか、マスク肌荒れ・マスクかぶれを実感する人も増えているようです。 1、マスク肌荒れの実態 企業によるマスク生活に関するアンケート調査では、1カ月にほぼ毎日マスク生活という人が約70%、さらには1年以内でマスクによるお肌トラブルを経験したことのある人は約3人に1人というほど、最近ではマスク生活によるお肌トラブルを感じている人が増えています。 ■マスク肌荒れの具体的症状 1、 湿度変化による皮膚炎 マスク内の温度変化によって肌荒れが起きる原因のひとつとして湿気による蒸れがあります。 湿度は一見お肌に潤いを与えてよさそうなイメージを持ってしまいがちですが、マスク着用による過剰な湿度ではお肌がふやけてしまい外部環境の影響を受けやすくなります。 暑い日は汗や皮脂の過剰分泌がかゆみを引き起こすこともあります。 マスク蒸れで発生した菌によって皮脂分解物が刺激となって「脂漏性皮膚炎」などの皮膚炎を発症してしまいます。 2、 マスクのつけ外しによる摩擦 日中飲み物を飲んだり、食事をしたりするときにマスクを外すこともありますが、このマスクのつけ外しのたびにお肌とマスクがこすれて、摩擦ダメージを受けています。 これによってかゆみやかぶれの原因となってしまいます。 3、 マスクを外したときの乾燥 ずっとマスクをしているとマスクの中は湿気で蒸れている状態ですが、これがマスクを外すことによって溜まった湿気が急激に蒸散することでお肌の中の水分まで一緒に奪われてしまうのがマスク乾燥です。 特にこれからの季節乾燥しやすい秋冬は余計に肌のかゆみを感じやすくなってしまうので注意したいシーズンです。 マスク荒れやかぶれを防ぐためには、マスクの内側で汗をかいたらこまめに拭いて、拭いたあとには保湿ケアをしっかりしましょう。 2、不織布マスクの肌荒れがつらいときに これまでは若年層でウレタンマスクが流行ったり、布や絹などデザイン性の高いマスクをしている人もよく見かけましたが、デルタ株の流行で不織布マスクを着用する人が増えてきました。 スーパーコンピューター富岳でもウイルス対策として最も有効なのは不織布マスクという結果も発表されました。 でも不織布マスクだけを着用したら、肌荒れがひどくなってしまったという人も少なくありません。 不織布マスクはウイルス対策としては有効でも、息苦しい・蒸れる・ごわごわするなどの着け心地ではウレタンマスクや布マスクに比べて気になるところもあります。 効果的でもお肌にダメージを与えてしまうのは悩ましいですね。 その対策として「二重マスク」もおすすめです。 夏の暑い季節は避けたい二重マスクですが、これからの秋冬シーズンであれば可能かもしれません。 ・不織布マスクの下に1枚あることで、不織布が直接に触れなくなる ・蒸れをもう1枚のマスクに吸収させることでさっぱりした使用感になる ・2重にすることでフィルター機能が強化できる ・汚れてもすぐに替えられるため衛生的 二重マスクをするときには、吸湿性・通気性がよく肌に優しい素材がおすすめです。 肌荒れが気になる方も安心して使えるシルクなどもよいでしょう。 ワクチン接種は進んでいるものの、もうしばらく続きそうなマスク生活。 少しでも快適かつ健康に、そして肌荒れを防ぎながら過ごていきたいですね。 授業、ゼミの様子やコラムが盛りだくさん! >>ほかの鍼灸学科コラムはこちらから まずは日本医専について知ろう! >>日本医専の資料請求をする]
-
 2021/10/08王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」
2021/10/08王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】第10弾「秋の食欲コントロール法」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 王先生コラムの第10弾をお届けいたします! 秋の食欲コントロール法 本格的な秋が到来です。 秋といえば、スポーツの秋、読書の秋など色々ありますが、なんといっても食欲の秋でしょう。 食欲があって、好きなものを好きな分だけを食べるのが幸せのことですが、その延長線上に心配されるのが体重の増加、ひいていえば肥満のことです。 では、今回のコラムは、秋の味覚を美味しくいただけて、かつ食べ過ぎない方法を解説してみます。 1.秋に食欲旺盛の東西医学の視点 秋に食欲旺盛のメカニズムは、西洋医学の考え方として主に三つが挙げられます: ① 気温が下がるため 私たち人間は、一定の体温を保とうする「恒温動物」です。 気温が下がると体から熱が奪われるため、放っておくと体温がどんどん下がってしまいます。 そうならないように体内で熱を作り出すよう、体は自然に調整するのです。 その熱を作り出すエネルギー源は食事ですので、気温が下がり始める秋に食欲が増します。 ② 日照時間が短くなるため 人間は日光を浴びると、「セロトニン」という物質の分泌が増えます。 セロトニンには気持ちの安定を保たせ、目を覚ましておく働きと食欲を抑える働きがあります。 秋は夏に比べて日照時間が短くなり、セロトニンの分泌も少なくなるため、食欲が抑えられずについ食べてしまうのです。 ③ 夏バテを解消するため 夏は室内と室外との温度差が大きいため、自律神経の調整が追い付かずに「夏バテ」になりがちです。 夏バテに陥ると食欲不振や疲れやすさ、だるさの不調に見舞われます。 しかし、秋になって涼しくなると、体調が回復して食欲も戻ってきます。 夏バテからのリバウンド効果ともいえるでしょうか。 一方、中医学の考え方として挙げられるのが「胃熱」です。 中医学でいう「胃」は主に消化を担う働きがあります。 胃に熱をこもると、食欲旺盛で食べてもまたすぐにお腹が空き、口臭、口が渇きやすい、歯肉炎、便秘などの症状が見舞われます。 胃熱がある場合、は普段からも食欲旺盛ですが、秋にさらに食欲が増す恐れがあります。なぜならば、夏に比べて秋は湿気が少なく、乾燥しやすいため、胃熱を助長しやすく、ますます食欲が旺盛になりやすいのです。 2.秋の食欲を抑える生活習慣・ツボ・食材 A.秋の食欲を抑える生活習慣: ① 早寝早起き、朝日を浴びる 早寝早起きをし、早朝に起床したらすぐに10分間ほど朝日を浴びると、前述した食欲を抑える働きのセロトニンの分泌が促進されるばかりでなく、日中に元気よく活動し、夜にぐっすり眠れることにもつながります。 ② よく噛んで食べる 食事の時によく噛んで食べると、食欲を抑える満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防いでくれます。 また、よく噛んで食べると唾液がより多く分泌されるから、前述した「胃熱」を鎮めることにもつながります。 ③ リズムカルな運動 ウォ―キングやジョギング、水泳、ヨガなどのリズムカルな運動は、食べ過ぎによる過剰なカロリーを消耗してくれるだけでなく、食欲を抑えることにもつながります。 休日に家でゴロゴロするだけでいると、食べることばかりに走ることになりがちです。 B.秋の食欲を抑えるツボ ① 耳ツボ:飢点・胃:食事の15~20分前に人差し指でやや強めに押す。 ② 内庭:胃熱を取るツボとして知られています。 C.秋の食欲を抑える食材 ① キノコ類 キノコ類は秋の味覚の一つで、ビタミン類や食物線維が豊富で低カロリーです。 キノコ類をしっかりと噛んでから食べることにより、食べ過ぎ防止につながります。 ② クマザサ クマザサは胃熱を取る働きがあるとされ、食べてもまたお腹が空くのに働きかけます。 また独特の香りにリラックス効果もあります。 ③ セロリ シャキッとした歯応えで、ビタミン類や食物線維が豊富で、胃酸の分泌を抑える成分が含まれています。 特有の香り成分はストレス緩和作用があり、ストレスに起因した食べ過ぎに効きます。 肥満に気を付けながら、美味しく秋の味覚をいただきましょう。 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 秋の食欲を抑えるツボとしてご紹介した耳ツボをオープンキャンパスで詳しくご説明します! ★鍼灸学科オープンキャンパス★ 10/30(土)14:00~16:00「耳ツボダイエットと美容鍼灸」 皆さまのご来校を心よりお待ちしております! ★まずは日本医専を知ろう!★ ≪日本医専の資料請求はこちら≫]
-
 2021/09/30その他
2021/09/30その他- 【コラム】不眠症について
-
こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は『不眠症』について解説します。 1、 不眠症は国民病?! 厚生労働省の調査では、日本人の5人に1人が「睡眠で休養が取れていない」「何らかの不眠がある」と回答してします。 さらに加齢とともに不眠は増加していくため、60歳以上の方では約3人に1人が何らかの睡眠問題に悩みがあるようです。 実際に睡眠の悩みで通院している方の20人に1人は不眠のため、睡眠薬を服用しているという調査結果でした。 今や不眠症は特殊な病気ではなく、国民病とも言えるほど、よくある普通の病気です。 さらにはコロナ禍で生活のリズムか崩れて、眠れなくなった方も増えてきているようです。 2、 不眠症の4つのタイプ 不眠症の定義とは、「眠れないなどの睡眠問題が1カ月以上続き、日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気」です。 この不眠症には大きくわけて4つのタイプに分けられています。 ① 入眠障害(なかなか寝付けない) ② 中途覚醒(眠りが浅くて夜中によく目が覚める) ③ 早朝覚醒(朝早くに目が覚めてしまう) ④ 熟眠障害(ぐっすり眠った感じがしない) 睡眠時間には個人差がありますが、日本人の平均睡眠時間は7時間程度です。健康な人でも年齢とともに「中途睡眠」や「早朝覚醒」が増えてきます。 不眠症とは、不眠というだけでなく日中に不調が出現することが問題です。 3、 不眠症の原因 不眠症は1つの病気ではなく、大部分の不眠症はそれぞれ原因があります。 ① 仕事や家庭環境・人間環境によるストレス ② 睡眠習慣の問題や睡眠リズムの崩れ ③ うつ病や適応障害などの精神疾患 ④ 睡眠障害無呼吸症候群や脳神経疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患 ⑤ アルコールや薬の影響によるもの ⑥ 周囲の環境(寝室の温度湿度・騒音・光など) 多くの場合、周囲の環境によるストレスや変化、睡眠リズムの乱れや睡眠障害が原因です。 なかでも、睡眠時無呼吸症候群・レストレスレッグス症候群・周期性四肢運動障害・うつ病による不眠は専門施設での検査や診断をおすすめします。 4、 不眠症への対処法 不眠症の対処法の第一歩は先に述べたようにさまざまな不眠の原因を診断して、取り除くことです。そして、自分に合った安眠法を工夫して、睡眠の質をあげるための生活習慣や睡眠リズムを整えるとよいでしょう。 ① 就寝・起床時間を一定にする ② 睡眠時間にこだわらない ③ 太陽の光を浴びる ④ 適度な運動をする ⑤ 自分なりのストレス解消法を見つける ⑥ 寝る前にリラックスタイムをつくる ⑦ 寝酒はNG ⑧ 寝室は快適な環境作りをする 眠れない日が続くと不安になり、焦れば焦るほど目が冴えて、さらに不眠恐怖への悪循環に繋がってしまうこともあります。 大切なことは眠れないことを一人で抱え込まないことです。自分に合った安眠法を探したり、専門家に相談するなど解決策を丁寧に探していきましょう。 この秋は、ぐっすり眠れますように。 授業、ゼミの様子やコラムが盛りだくさん! >>ほかの鍼灸学科コラムはこちらから まずは日本医専について知ろう! >>日本医専の資料請求をする]
-
 2021/09/27王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」
2021/09/27王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】第9弾「秋と肺」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 王先生コラムの第9弾をお届けいたします! 秋と肺 草花に朝露がつき始める二十四節気の白露が過ぎ、本格的な秋が到来しています。 秋といえば、世間では「食欲の秋」、「読書の秋」などのイメージがありますが、東洋医学では、秋は五臓六腑の肺と最も関係し、この時期は特に肺に対してケアすることを心掛けてほしいと考えています。 朝晩の冷え込んだ秋に、屋内から屋外に出るとくしゃみや鼻水が出たり、風邪を引いたりするようなことがありませんか? また、鼻や口の中が乾燥して、のどがイガイガしく感じることがありませんか? それらの症状が出やすい方の場合は、季節の変化に応じて調整し体表をガードしてくれる肺の機能がダウンしている可能性があると、東洋医学的に考えています。 そもそも、秋は①朝晩と日中の寒暖差が激しい、②夏より空気が乾燥している、この二大特徴があります。 この特徴は、デリゲートな性質を持ち、外気に通じ、五臓六腑の一番トップの位置にある肺を傷ついてしまう恐れがあります。 従いまして、秋の時節の変化より肺を守る養生法で過ごしていただきたいものです。 ①秋の寒暖変化から肺を守る方法 ・マスクをして冷たい空気を遮断し、重ね着して気温の変化に応じて衣服を調整するように。 ・手首にあるツボ「太淵(たいえん)」を押したりして刺激する。 ・生姜湯を飲む。 ・漢方処方:玉屏風散 (ぎょくへいふうさん)、補中益気湯(ほちゅうえっきとう) ②秋の乾燥から肺を守る方法 ・秋の旬の食べ物の梨、ぶどう、柿、蓮根、ゆり根などが、いずれも肺に潤いを与えるものとして知られています。 ・漢方処方:麦門冬湯(ばくもんどうとう) コロナ禍で、未だに収束の見通しが立たない今、これまで以上に肺のことを意識し、ご紹介した方法を活用していただければ幸いです。 (監修/王瑞霞 先生) 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 王先生はオープンキャンパスも担当しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 ★鍼灸学科★ 10/3(日)13:00~15:00「やさしい鍼でリフトアップ!美容鍼灸の効果」 10/9(土)14:00~16:00「基礎からわかる美容鍼灸 ~綺麗なすっぴん素肌の作り方~」 皆さまのご参加を心よりお待ちしております! ★まずは日本医専を知ろう!★ ≪日本医専の資料請求はこちら≫]
- 訪問者別
- 採用ご担当者の皆さまへ
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







