-
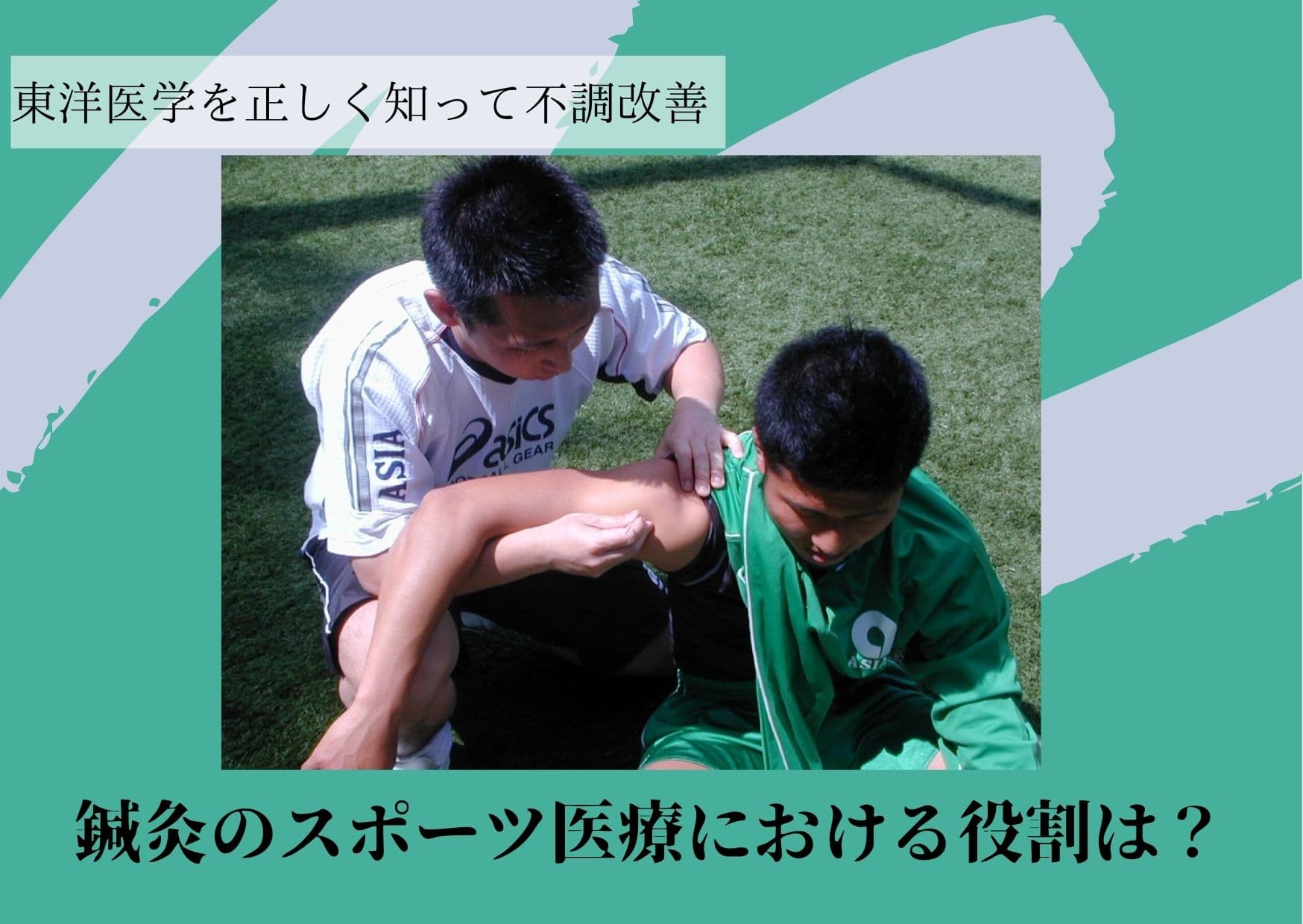 2022/07/06その他
2022/07/06その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十六回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十六回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 鍼灸のスポーツ医療における役割は?取り入れる選手も多い 東洋医学では古くから「未病」という考え方があります。 未病とは病気になりそうな状態であり、そんな状態を察知し対策を講じることで、バランスの取れた健康な状態に戻す。 これを、東洋医学では得意としているのです。 この考え方はスポーツ選手のパフォーマンス向上やコンディション維持に合致し、鍼灸を体調維持のために取り入れるスポーツ選手も珍しくありません。 実際に私が対処したケースを挙げると、大学のサッカー部の選手からパフォーマンスが上がらないという相談を受け、問診から睡眠時間が少ないと判断し、全身に週3回の鍼治療を行った結果、よく寝られて疲れなくなり、パフォーマンスが戻りました。 スポーツにおける鍼灸治療のサポートの重要性は今後も高まっていくものと考えられます。 まずは試してみて、もし自分に合っていると思われたようなら、今後、未病の対策のひとつに鍼灸を選んではいかがでしょうか。 <<記事全文はこちら>> 大島貞昭 先生(鍼灸学科専任教員) 柔道整復師・鍼灸師 スポーツ鍼灸ゼミ顧問 JFA公認ライセンスB級コーチ 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>日本医専の資料請求はこちら]
-
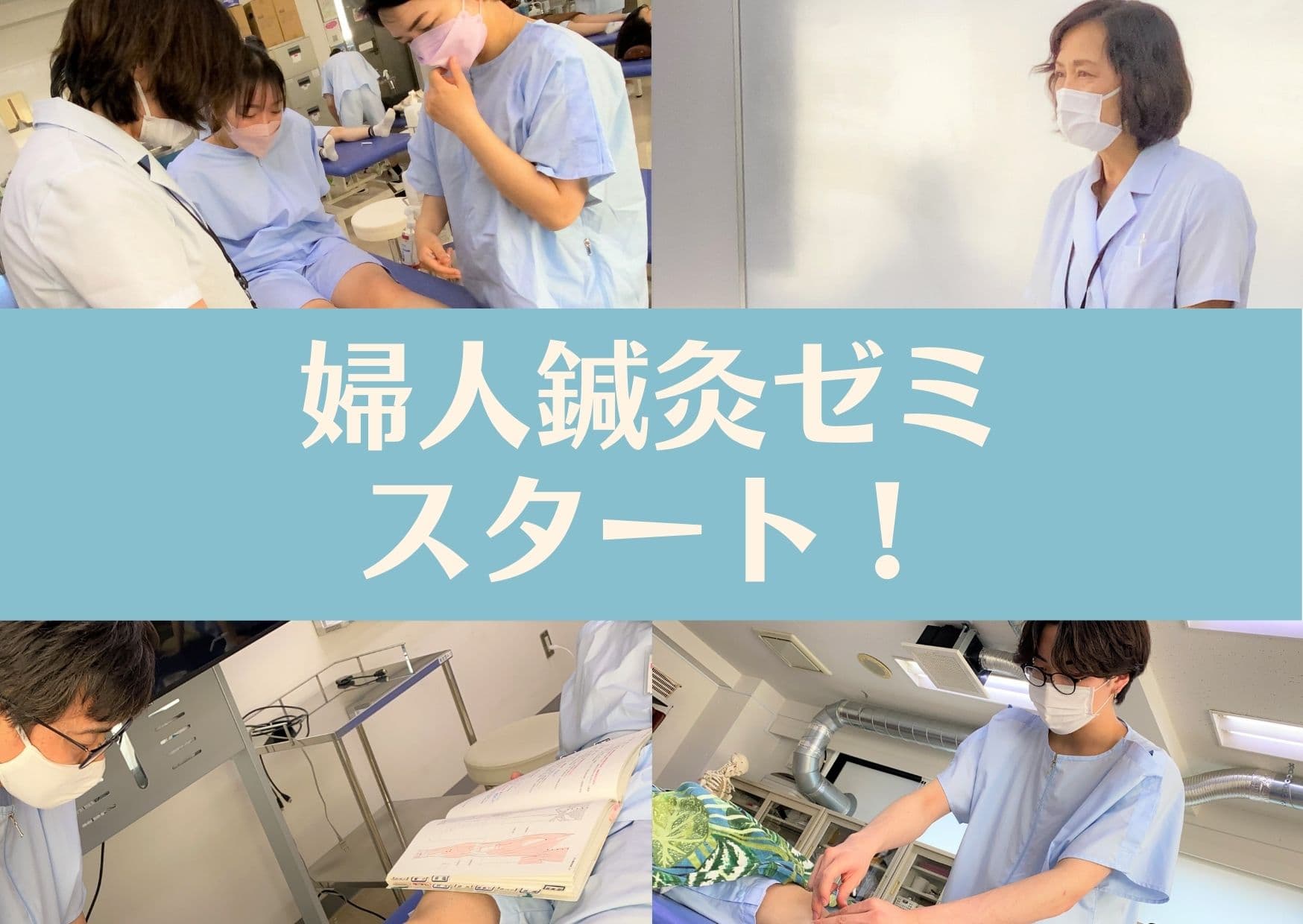 2022/07/01婦人鍼灸ゼミ
2022/07/01婦人鍼灸ゼミ- 婦人鍼灸ゼミが始まりました!
-
みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 4大鍼灸ゼミの1つ、婦人鍼灸ゼミが始まりました! 講師は鍼灸学科専任教員の王先生です。 本日は初回ということで、まずは王先生の自己紹介から始まり、学生たちの事前アンケートで聞いていた婦人鍼灸ゼミへの参加理由を紹介していきました。 「将来幅広い分野で活躍したいから」 「自分自身も婦人系疾患を抱えており、深く学びたかったから」 など、理由は様々でしたが、みなさん共通して“女性の悩みを解決したい”という強い意志を持っていました。 続いて、婦人鍼灸ゼミに参加する学生の今持っている技術を知るために、足三里(あしさんり)と上巨虚(じょうこきょ)のツボを、皮膚に対して直角に打つ直刺で練習していきます。 途中、王先生から刺鍼の時の体勢についてのお話しがあり、生徒1人1人に丁寧にアドバイスをしていきます。 通常授業以外で深く学べる4大鍼灸ゼミ。 自分のやりたい道で腕を磨き、「この先生はすごいよ!」と患者さんに言われるような鍼灸師になってほしいと王先生。 ゼミの回数を重ねるごとに成長する生徒のみなさんの姿を見られることが、とても楽しみです! オープンキャンパスでも、実際の施術を見たり鍼に触れることができるので、是非いらして下さいね♪ >>オープンキャンパスの予約はこちらから >>資料請求はこちら >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら]
-
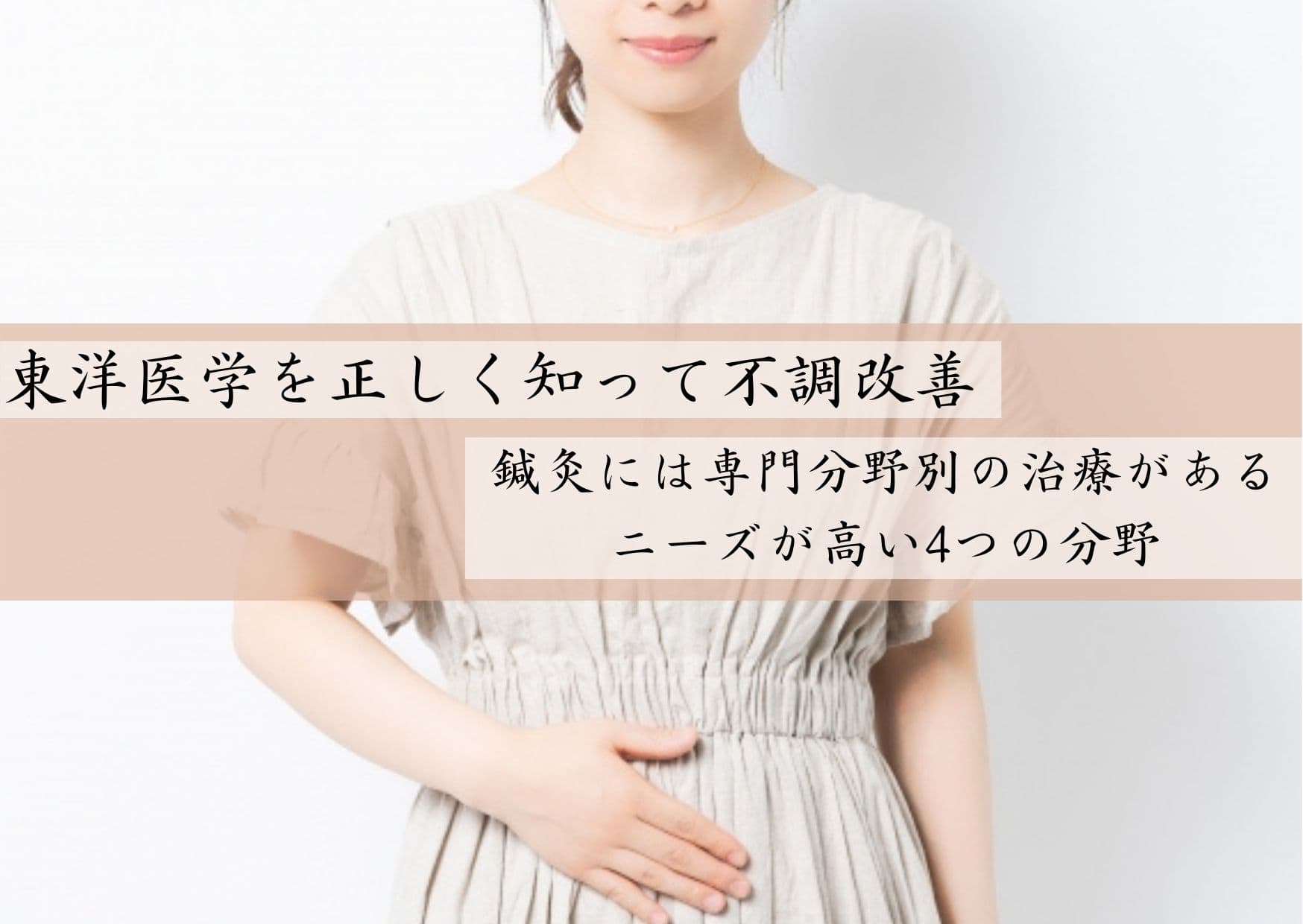 2022/06/29その他
2022/06/29その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十五回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十五回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 鍼灸には専門分野別の治療がある ニーズが高い4つの分野 鍼灸の特徴のひとつに、特定の分野で積極的に用いられていることが挙げられます。 特にニーズの高い4つの分野を紹介したいと思います。 まず1つ目がスポーツ分野です。 鍼は「血行改善」「筋緊張緩和」「鎮痛」の作用があり、自身の体の管理が重要なアスリートにとって、血行改善で疲労回復を早めたり、筋肉を緩めたりできる鍼灸は、ケガからの復帰やパフォーマンスの向上が期待できる治療法として認識されています。 2つ目は婦人科の領域です。 体のバランスを整えることを目指す東洋医学との相性が良いのです。 「不妊症」「更年期障害」「月経困難症」など婦人科領域では専門の鍼灸師が多く活躍しています。 3つ目は、近年ますますニーズが高まっている美容鍼灸です。 鍼は基本的に血行を良くし代謝を促す作用があるため、シワやたるみの改善につながるわけです。 体のバランスを整えることによる美肌効果も期待できます。 そして4つ目が、高齢者や小児分野です。 鍼灸は免疫力を維持・向上させることができるため、健康維持や病気の予防を目的に定期的に受診する高齢者もいるほどです。 子供を対象とした小児鍼では、刺さない鍼を用いて対処して、夜泣きに疳の虫や夜尿症などを得意としています。 近年では不登校や発達障害といった心の問題に対しても鍼灸が活用されています。 <<記事全文はこちら>> 中村 幹佑 先生(鍼灸学科専任教員) はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>日本医専の資料請求はこちら]
-
 2022/06/23その他
2022/06/23その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十四回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十四回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 東洋医学では「むくみ」をどうやって改善するのか? 医学用語では「浮腫」と表現されます。 浮腫とは、何らかの原因で細胞と細胞の間の液体(間質液)が異常に増加し、体外に十分に排泄されずたまった状態を指します。 浮腫の原因は人それぞれあり、内臓の疾患、長時間の同じ姿勢、水分の取り過ぎなどで起こることもあります。 東洋医学では気・血・水が体を巡っていると考えます。 この「水」にかかわる病態は非常に広範囲であり、中でも「浮腫」は、この水の異常と関係しています。 浮腫のセルフチェックとしては、東洋医学では舌の状態で判断することもあります。 その場合には、舌は胖大(腫れぼったく)、歯痕(舌に歯の痕がつく)、厚苔(舌に白っぽい苔が厚くなる)といったような状態が現れるとされています。 一般的な対処としてはマッサージやストレッチ、膝の下内側の陰陵泉といったツボを押すのも効果的です。 東洋医学的に水の流れを良くする、いわゆる利水作用のある食材、例えば昆布やもやしを食して、体の中からケアしていくことも効果があるとされています。 <<記事全文はこちら>> 徳江謙太先生(鍼灸学科専任教員) 鍼灸師 柔道整復師 介護支援専門員。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>日本医専の資料請求はこちら(デジタルパンフレットもあります!)]
-
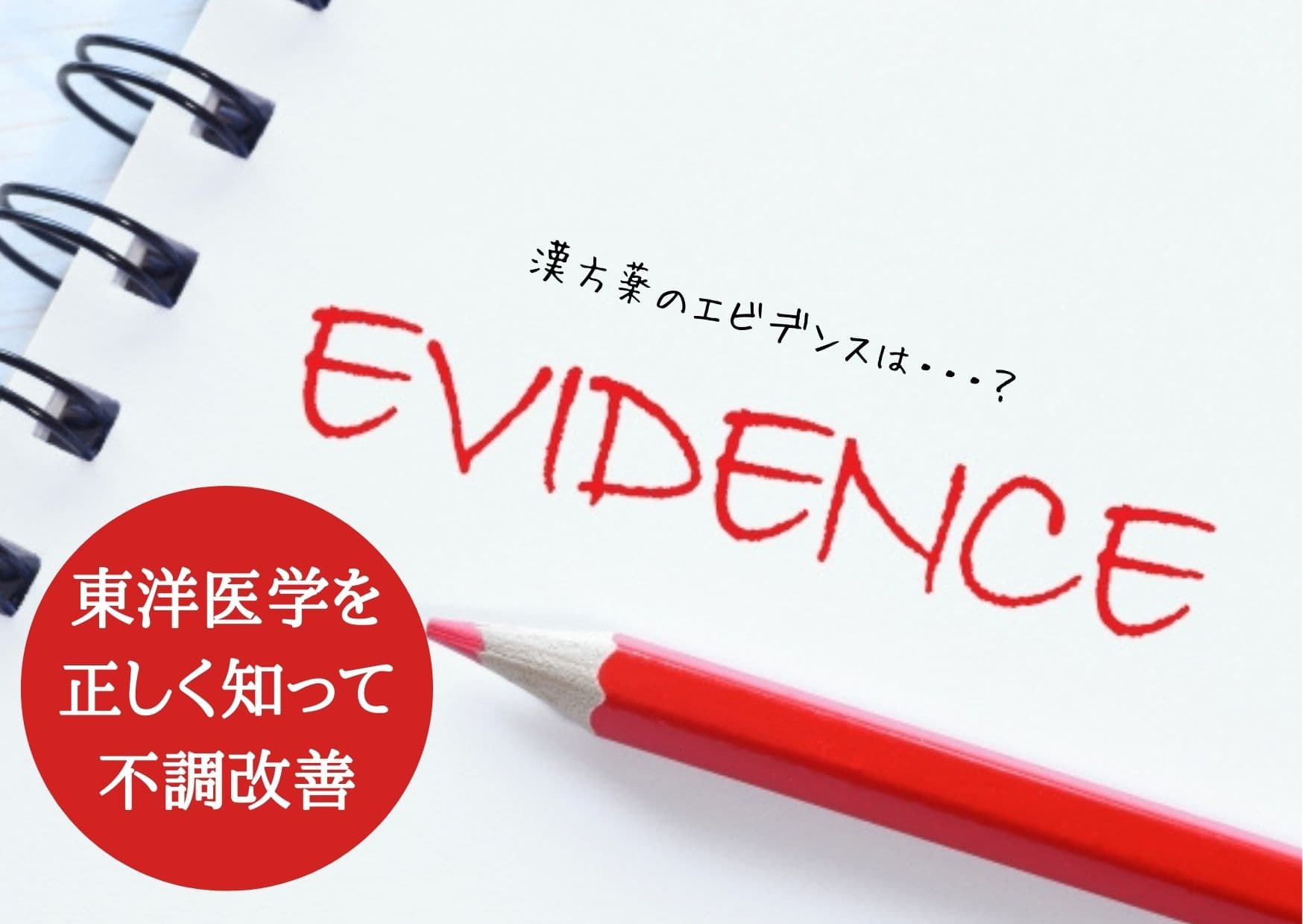 2022/06/15その他
2022/06/15その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十三回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十三回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 漢方薬はエビデンスに乏しいという批判的な声も聞くが実際は? 日本の医療はエビデンス(科学的根拠)に基づいたものが主流です。 エビデンスを取得するために動物実験やランダム化比較試験などが行われ、このうち最も信憑性が高くグレードもトップにあるのがランダム化比較試験になります。 一方、医療用漢方(医師が処方する保険適用の漢方)は長年の臨床経験をもとにしており、ランダム化比較試験が行われていません。 そのため「漢方薬はエビデンスに乏しい」といった批判的な見方が医師の間でも根強く存在していました。 これに対応するため、日本東洋医学会は2001年、エビデンス委員会を設立。 積極的に漢方薬のエビデンス研究を行い、結果を発表しています。 しかしながら、漢方薬はエビデンスを解明するのが難しい薬でもあります。 たとえば糖尿病を例に挙げると、西洋医学では発病のメカニズムを分析し、インスリンの働きの鈍さによるものであれば、そこにピンポイントに作用する薬を開発し、同じ病態の糖尿病であれば、同じ薬を使います。 ところが漢方薬では、症状と患者の体質から「証」を判断し、証に合った漢方薬を使います。 同じ糖尿病であっても証が異なれば、使う薬も異なるのです。 研究者の努力で漢方薬のエビデンスの構築が進んでいます。 漢方薬において、「エビデンスが乏しい=効き目が良くない」というわけでは決してないのです。 <<記事全文はこちら>> 王 瑞霞先生(鍼灸学科専任教員) 医学博士、中医師、鍼灸師 中国山東中医薬大学卒業 中国北京中医薬大学大学院修了 日本大学医学部医学博士 中国では伝統医学医師資格である中医師の資格を有して、日本では長年、漢方薬、鍼灸の医療現場及び教育に携わる。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>日本医専の資料請求はこちら(デジタルパンフレットもあります!)]
-
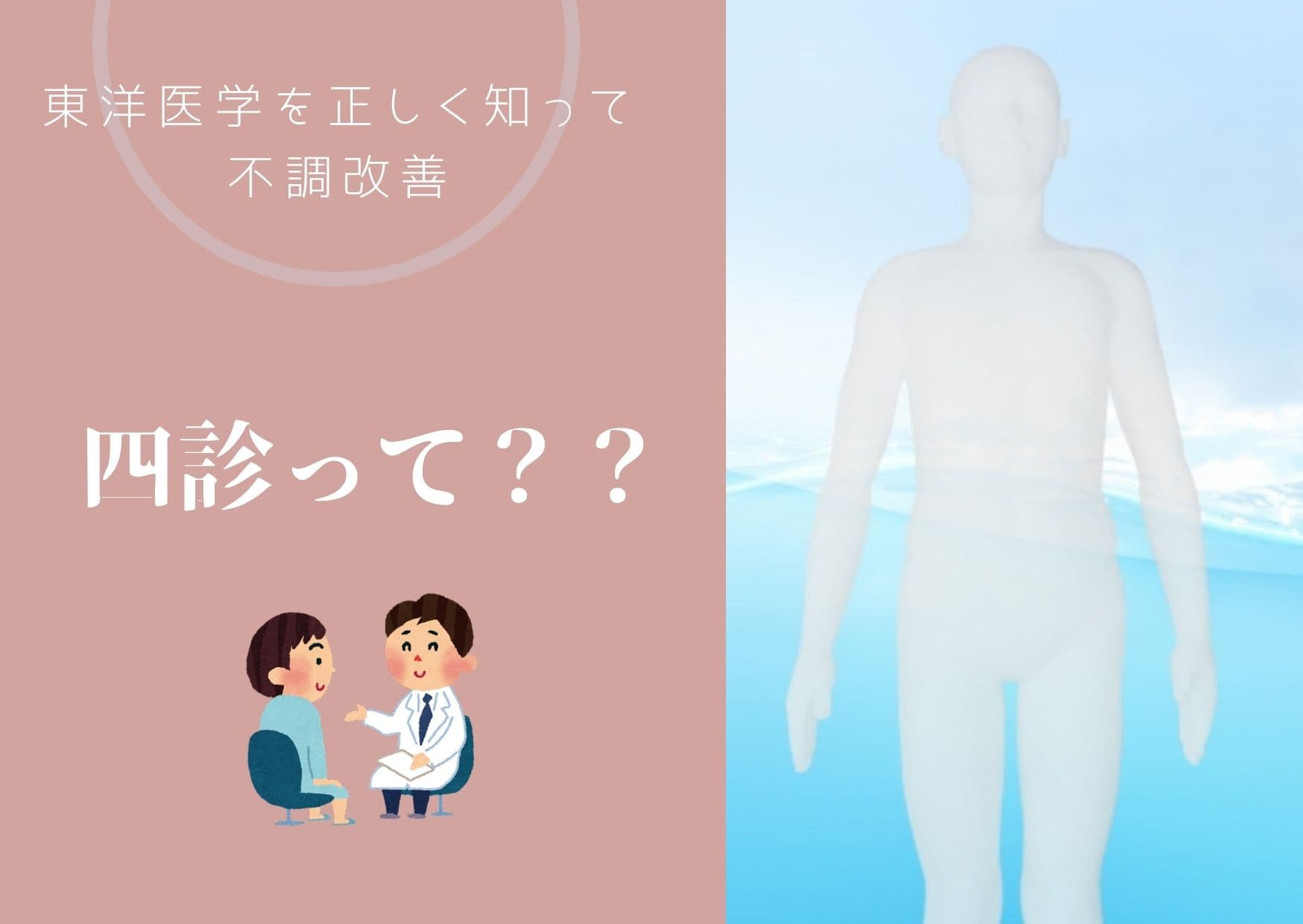 2022/06/09その他
2022/06/09その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十二回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十二回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 東洋医学の独特の診察法「四診」とはどのようなものなのか 東洋医学では、気血水、臓腑、経絡がバランス良く働いている状態を健康と考えます。 バランスの失調は、「実」「虚」として表現されます。 「実」には、不要なものの解消や機能高進を改善させる「瀉」、「虚」には文字通り補う「補」という治療方針が取られます。 東洋医学における治療とは、生体の不均衡を見つけ出し整える行為といえます。 不均衡を見いだすために、望診(見る)・聞診(聞く・嗅ぐ)・問診・切診(触れる)を行い、これら診察はまとめて四診と呼ばれます。 望診では、顔や皮膚の色つや、形態の変化、たたずまいなどを見ます。 舌の状態を見る舌診も望診のひとつです。 舌診では、色・形や舌苔(舌表面に生じる苔状のもの)などを観察します。 体に触れて行う切診には経絡やツボの診察のほか、脈診や腹診もあります。 動脈拍動には体の状態がよく表れ、これを診察に用いるのが脈診です。 腹部を診察する腹診は、全身状態や虚実を判定したり、処方や施術部位決定の指針とします。 「目で見ることができない体の働きをいかに体表から捉えるか」ということは、治療法と並ぶ最重要事項です。 東洋医学の長い歴史の中で、医家たちは自らの五感を研ぎ澄まして診察し、その経験を積み重ねてきました。 現代では、このような東洋医学の診察法を駆使し、かつ西洋医学の知識もあわせ、病を診察し治療を行っているのです。 <<記事全文はこちら>> 天野陽介先生(鍼灸学科専任教員) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員も務める。 日本伝統鍼灸学会、東亜医学協会、全日本鍼灸学会、日本医史学会、日本東洋医学会所属。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>日本医専の資料請求はこちら(デジタルパンフレットもあります!)]
-
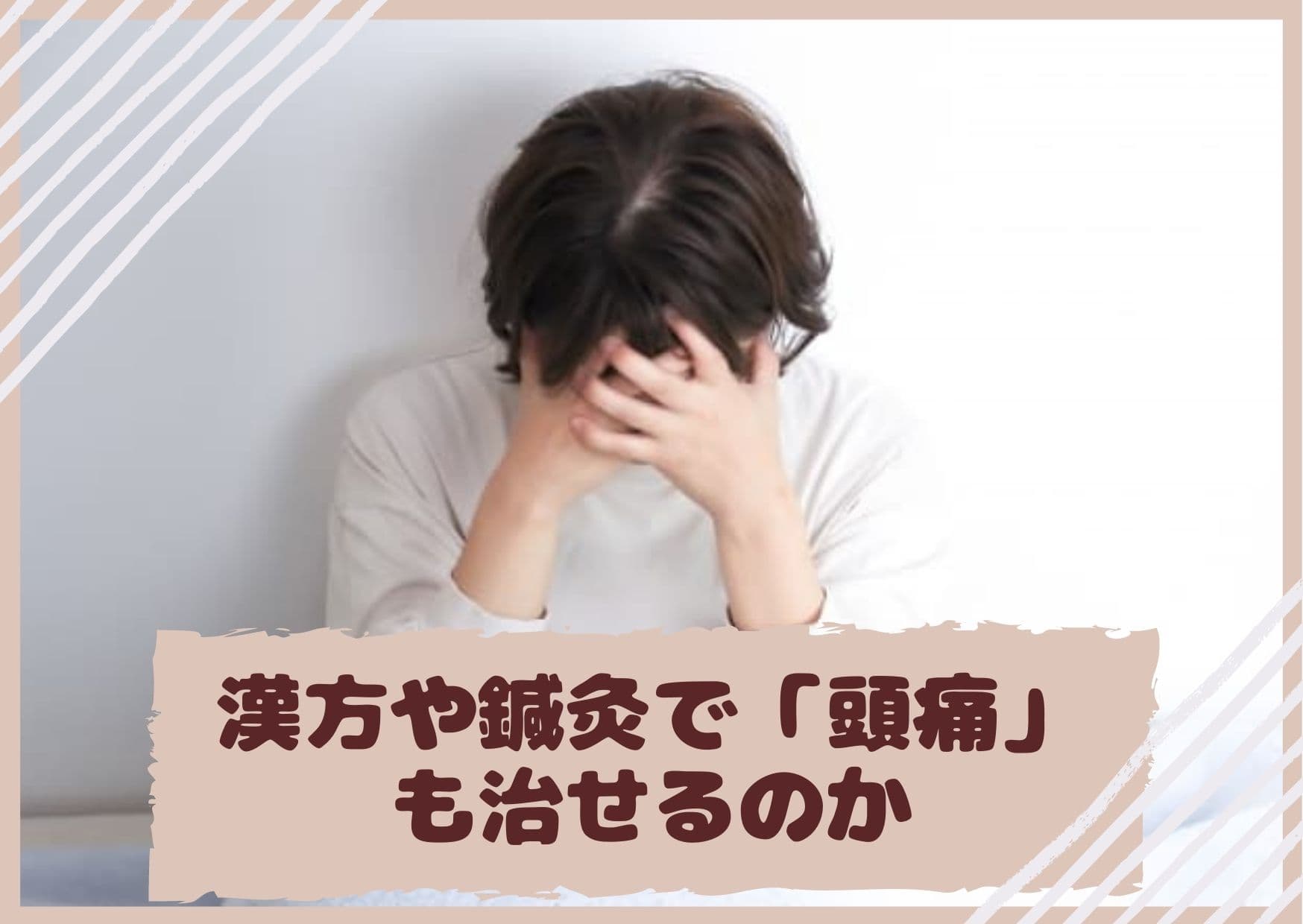 2022/06/02未分類
2022/06/02未分類- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十一回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十一回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 漢方や鍼灸で「頭痛」も治せるのか “一次性”が治療対象 頭痛は頭部に感じる痛みの総称で、後頭部と首の境界、目の奥の痛みなども含まれます。 非常に多くの方が経験している症状です。 原因が特定できないものを「一次性頭痛」。緊張型頭痛、片頭痛、群発性頭痛などが該当します。 脳血管障害など原因疾患が特定できるものは「二次性頭痛」といいます。 頭痛を訴える人の多くは一次性頭痛が多いかと思われますが、東洋医学で頭痛の主な治療対象となるのは、この一次性頭痛です。 片頭痛の場合、漢方の処方でいえば、前触れとしてむくみが、そして回復期には利尿が表れることから、体の中の水の滞り(水滞)を改善させる生薬「五苓散」や「呉茱萸湯」を用い、月経時に伴う血の滞りを改善させるには「当帰芍薬散」や「桃核承気湯」という生薬がよく用いられます。 指先を揉むことでも効果あり 鍼灸治療となると、頭痛が起こる部位によって分類し、体にめぐる気・血・水の循環経路である経絡に基づいた施術が行われます。 この経絡に関していえば指先を揉むことでも効果があり、たとえば「太陽経頭痛」は手足の小指、「陽明経頭痛」は人さし指、「少陽経頭痛」は薬指、「厥陰経頭痛」は手の中指と足の親指がよく効きます。 日頃からおうちで揉んでみて気持ちが良い、効きそうな指を刺激することもいいでしょう。 <<記事全文はこちら>> 天野陽介先生(鍼灸学科専任教員) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員も務める。 日本伝統鍼灸学会、東亜医学協会、全日本鍼灸学会、日本医史学会、日本東洋医学会所属。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
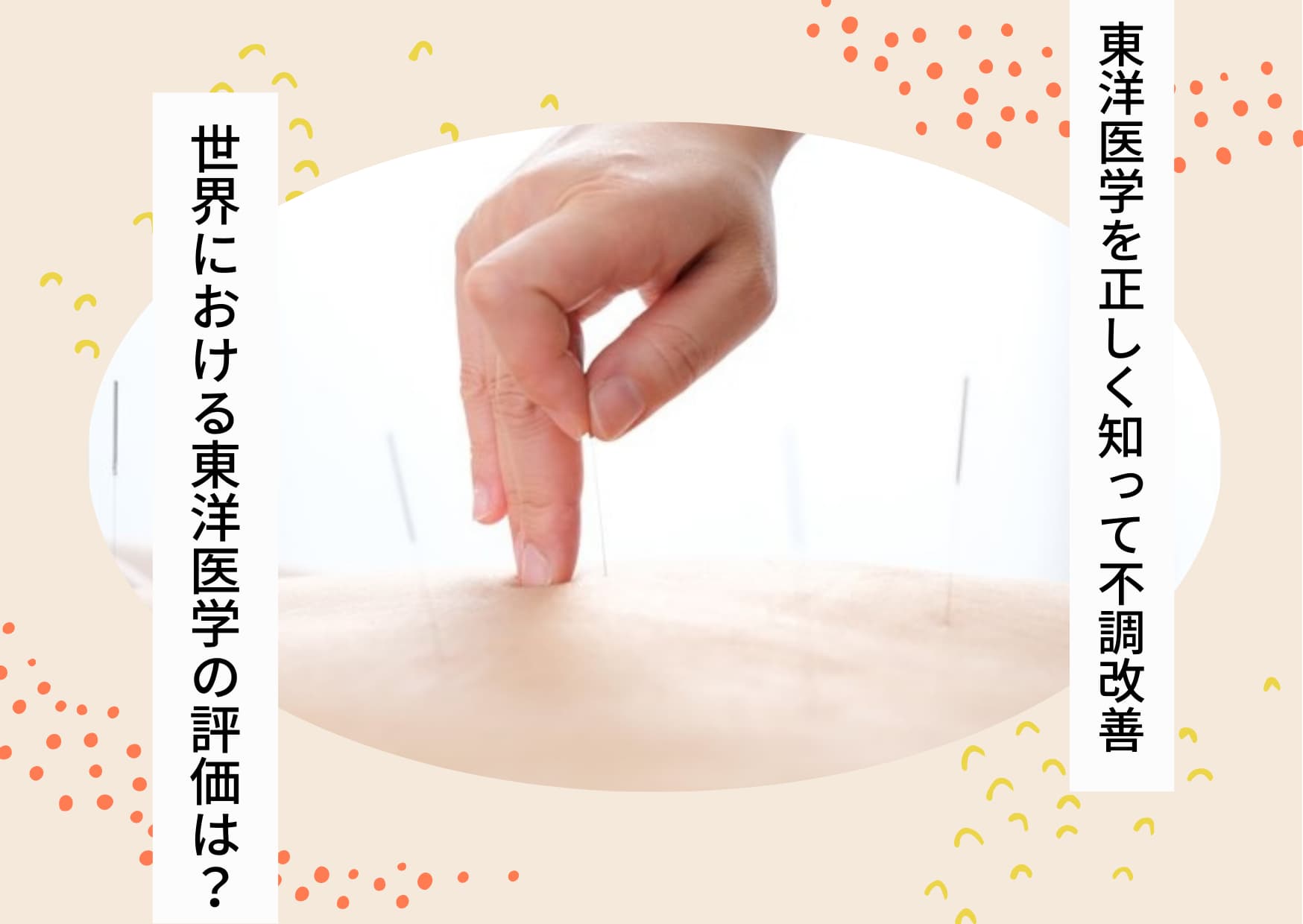 2022/05/25未分類
2022/05/25未分類- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第二十回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第二十回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 世界における東洋医学の評価は? 欧米で注目度が高まっている これまでにも「東洋医学」はさまざまな体の不調に対処できる治療法として紹介してきましたが、近年になって西洋医学では手が届かなかった症状への解決策として、世界中で注目を集め始めています。 中でも先進医療が発達する米国では、鍼治療の導入が盛んです。 例えば鍼灸治療が、腰痛のガイドラインで紹介されています。 65歳以上の公的医療保険制度でも鍼治療が正式に採用されています。 こうして東洋医学が米国を中心に注目され始めた背景には、いま米国社会で大きな問題となっている「オピオイド(鎮痛薬)」の乱用による薬物中毒問題があります。 痛み止めに気軽に鎮痛薬を服用することで、薬物中毒が多発し、年間数万人の死者が出るほどの深刻な社会問題となっており、薬物に頼らないで「痛み」を緩和する手段として、鍼治療の研究と導入がにわかに進んでいるというわけなのです。 これまでベールに包まれていた「東洋医学」の治療メカニズムが、徐々に科学的にも効果が裏付けられた治療法として、解明され、今後も世界中で認められていくことでしょう。 <<記事全文はこちら>> 天野陽介先生(鍼灸学科専任教員) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員も務める。 日本伝統鍼灸学会、東亜医学協会、全日本鍼灸学会、日本医史学会、日本東洋医学会所属。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
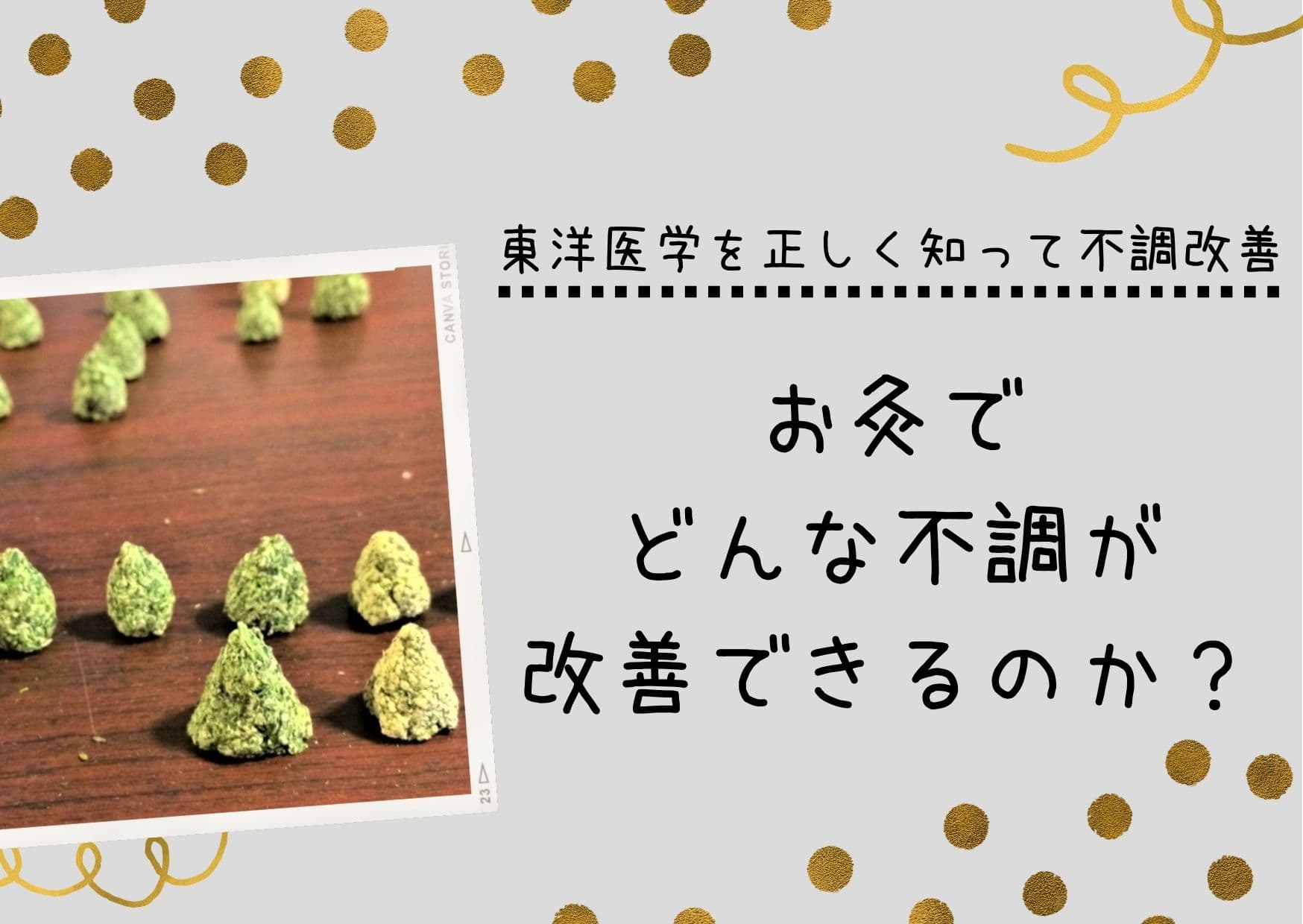 2022/05/19その他
2022/05/19その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第十九回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第十九回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! お灸でどんな不調が改善できるのか? 冷えに関係する症状に強い お灸は温熱効果によって、自然治癒力や免疫力を向上させ、それにより病を防ぎ治していく治療法です。 あらゆる不調に対し、改善効果が期待できます。 特に得意とするのが、体の冷えと関係の深い不調です。 具体的には、関節や筋肉の痛み、神経痛、便秘や下痢といった消化器症状、更年期障害・不妊症・月経痛などの婦人科系疾患などになります。 単純にどこにでもお灸をすればいいというものでもありません。 いわゆるツボと組み合わせることでその効果を発揮するのです。 そのほかにも「痔」や「ものもらい」といったものまで、それぞれに応じた特定のツボにお灸をすえ、治療ができます。 このようにあらゆる病気に対処できるのがお灸です。 気になる方はお近くの鍼灸院で相談してみてください。 <<記事全文はこちら>> 中村 幹佑 先生(鍼灸学科専任教員) はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師。 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2022/05/11その他
2022/05/11その他- 日刊ゲンダイヘルスケアにて連載中!「東洋医学を正しく知って不調改善」第十八回
-
みなさん、こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本校鍼灸学科教員が執筆する「東洋医学を正しく知って不調改善」の第十八回が日刊ゲンダイヘルスケアに掲載されましたので、ご紹介します! 苦くて不味い…漢方薬の味が苦手な人はどうすればいいのか 昔から「良薬は口に苦し」と言うことわざがあるように、漢方薬は苦くてまずいのが当たり前……と思っている方は多いのではないでしょうか? 漢方薬は処方によって、独特な気味(味とにおい)を醸し出しており、それによってあの漢方薬独特の味が生まれているわけです。 中でも土瓶や土鍋で水に入れ火にかけて煎じる「煎じ薬」は、生薬の原料をそのまま煎じてできた液体を飲むため、最も飲みづらいものです。 この最も飲みづらい煎じ薬を飲みやすくするには、蜂蜜または牛乳などを少し加え、少量ずつ数回に分けて飲むとか、また冷たくなると苦みを感じやすくなる傾向があるため、ぬるま湯で飲んでみたりするなどです。 それでも飲めないとおっしゃる人は、ひょっとしてその漢方薬がその人に合っていないのかもしれません。 多くの場合その人の体質に合っていれば、それほどまずいと感じずに比較的楽に飲めるケースがあるからです。 したがって、上記の対処方法を試しても、なお飲めない場合は、医師や薬剤師に相談して、漢方薬を変えてみることをお勧めします。 <<記事全文はこちら>> 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの鍼灸学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
- 訪問者別
- 採用ご担当者の皆さまへ
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







