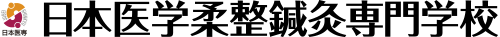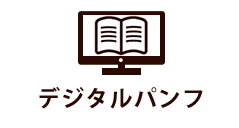中医学(中国の医学)では、「鍼灸」と「漢方薬」の大きな2本の柱があります。
実際に中国の中医薬大学でも、この2つの医学で病気の治療をしています。
「鍼灸」×「漢方薬」は両方を組み合わせることで両輪効果が生まれるのです。
鍼灸師について
鍼灸×漢方
中医学とは
中医学には、「整体観」と「弁証論治」という考え方があります。 中医学の特徴でもあるこの2つについてご説明します。
●「整体観」
人の体は自然から影響を受ける存在であり、また人の体の内部でもさまざまな部位が影響し合うという考え方です。
五臓(肝・心・脾・肺・腎)は単独で働いているわけでなく、それぞれが協調して働くことで正常な動きを保っている、逆に1つの臓器の働きが乱れると他の臓器にも影響を及ぼしてしまうと考えます。そのため、病気だけを診るのではなく人間を全体として捉えて、その病気の症状が1つの臓器(部位)であったとしても局所だけの問題なのか?ほかの臓器とも関連して起きていることなのか?というふうに、体全体を診て治療をします。
中医学では全体のバランスを整える治療であると言えるでしょう。
●「弁証論治」
中医学における弁証論治とは、病気の原因や経過を分析することで体がどのような状態になっているかを判断して、その体の状態に応じた治療法を選択するというものです。
中医学には、『同病異治』・『同病同治』という言葉があります。同じ症状でも原因が違えば治療方法は異なり、違う症状でも原因が同じであれば治療方法は同じになるという意味です。
中医学の1本の柱である鍼灸では、このような中医学の考え方を基にして、体の状態を診て、治療方針を決めます。それに応じて、経絡や経穴(ツボ)を選択して鍼灸治療をおこないます。
気血津液とは
中医学では、人の体は「気」・「血」・「津液」という3つで構成されていると考えています。
それぞれの働きを説明します。
●「気(き)」の働き
- ①体の栄養となる働き
- ②臓器の働きを調整したり、血液や経絡のめぐりを促進する働き
- ③体を温める働き
- ④免疫機能の働き
- ⑤汗や出血などにより体液や血液が外へ漏れ出ることを留める働き
- ⑥体の物質を代謝してさまざまな物質を相互転換させる働き
●「血(けつ)」の働き
- ①身体の栄養
- ②潤す
- ③精神活動を支える栄養源
●「津液(しんえき)」の働き
- ①身体を潤うきれいな水の総称
血液以外の唾液、胃液、涙、肝などです。
水分である津液が不足すると喉の渇きや皮膚の乾燥につながり、排せつ滞って、むくみや痰の症状につながるという水液です。
経絡経穴とは
経絡経穴(けいらくけいけつ)という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
・ツボ=経穴
・気血が流れる通路=経絡
では、鍼灸治療ではどうしてツボに鍼やお灸をするのでしょうか?
鍼灸師はツボに表れた反応を診ることで、五臓六腑のどこに不調が現れたのか見つけることができます。ツボと五臓六腑が経絡によってつながっているので、ツボに鍼やお灸をするとその刺激が経絡に伝わって体の調子を整えることができるのです。
つまりツボというのは、体の好不調の反応が出る場所であり、治療点となる場所です。
漢方とは
私たちの日常生活でも浸透している「漢方」は、中国の医学から日本に伝わり、中国人だけでなく日本人の体や生活にも合うように長い歴史の中でアレンジされたものですので、元々は中医学が基本となっています。
中医学では、現代のようにさまざまな検査機材がないなかで人間の持つ五感を活用した『四診』という方法を用いて体の状態を診断してきました。
●四診とは
「問診」:患者の主訴、病歴、病状を聞く
「切診」:脈や体の状態を触れて診断する
「望診」:顔色、舌、皮膚の状態を診て診断する
「聞診」:呼吸音など嗅覚や聴覚を使って診断する
中医学の特徴は“個を重視した医療”です。
西洋医学では治療の際に、病名や検査データをもとに治療をおこないますが、中医学は病名ではなく、体に現れるさまざまな状態を総合的に考える「証」をもとに治療法を決定します。
例えば、西洋医学では痛みがあるときには鎮痛剤を使いますが、中医学では痛みがあるその人の冷えや熱感の有無や元気の有無などさまざまな状態を鑑みて治療法を決定します。
個人の体質にあわせて適した治療をおこなうことができるので、さまざまな疾患や症状に対応できるのです。
中医学の考え方では、病気になっている状態(=既病)だけでなく、病気を発病する前の状態(=未病)を治すことができると考えます。
症状は自覚するものですが、その根本には体力の低下や内臓の弱まりがあると考えます。
漢方薬は、薬のなかで唯一体質を強くすることで病気を治す働きがあります。ですので、中医学における未病の段階でも漢方を使えるのです。そして、漢方薬など薬物だけでなく、食事や生活習慣病などの養生法も中医学では確立されています。
鍼灸と漢方薬
このように、「鍼灸」と「漢方薬」の治療の特徴は、「鍼灸」は身体の機能を活性化させたり、老廃物をデトックスする働きが優れていることに対して、「漢方薬」は体力や栄養を回復させることに優れています。重要なことは、「鍼灸」と「漢方」が両軸で同じ目的で用いていることです。両方を上手に活用することで両輪効果が得られるのです。
日本では資格制度の関係で、鍼灸はおもに鍼灸師が施術をして、漢方薬は医師や薬剤師が処方します。日本における鍼灸治療は腰痛や神経痛など整形外科や神経内科などで施術されることが多いのは現状ですが、世界においては癌や難病などの多くの疾患にも用いられています。さらに、スポーツ界でもトップアスリートの身体メンテナンスに鍼灸治療を用いたり、最近では美容鍼灸という小顔や美肌など美容目的で鍼灸を受ける人も増えてきています。
これからの鍼灸師は、中医学から伝わる中国本場の中国鍼を使用した施術と、日本ならではの日本鍼を使用した施術の両方が使えることで、より患者の個にあわせた治療できます。
さらに鍼灸に加えて漢方の知識を持ち、中医学の両輪で施術ができる鍼灸師はより活躍の幅が広がると言えるでしょう。
鍼灸師についてさらに
詳しく知る
 鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など
鍼灸師とは?仕事内容や資格の取り方、就職先など 鍼灸師にはどんな魅力とやりがいがある?必要な資格や能力、適性は?
鍼灸師にはどんな魅力とやりがいがある?必要な資格や能力、適性は? 鍼灸師の現状と将来性
鍼灸師の現状と将来性 女性が活躍できる資格・鍼灸師
女性が活躍できる資格・鍼灸師 美容鍼灸とは?どんな効果がある?
美容鍼灸とは?どんな効果がある? 鍼灸師には通信教育でなれるの?
鍼灸師には通信教育でなれるの? 鍼灸師として独立開業はできる?
鍼灸師として独立開業はできる? 鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い
鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師との違い
 中国鍼灸と日本鍼灸の違い
中国鍼灸と日本鍼灸の違い 婦人鍼灸とは
婦人鍼灸とは 鍼灸師のスキルアップに役立つ資格とは
鍼灸師のスキルアップに役立つ資格とは 鍼灸師の1日のスケジュールって?
鍼灸師の1日のスケジュールって? 鍼灸師の年収、月収はどのくらい?
鍼灸師の年収、月収はどのくらい? 鍼灸師になるには?合格率や難易度
鍼灸師になるには?合格率や難易度 スポーツ鍼灸とは ~スポーツトレーナーとして活躍する鍼灸師~
スポーツ鍼灸とは ~スポーツトレーナーとして活躍する鍼灸師~ スポーツ鍼灸の効果と施術方法
スポーツ鍼灸の効果と施術方法 免疫力を高める鍼灸 ~コロナに負けない~
免疫力を高める鍼灸 ~コロナに負けない~ 鍼灸の効果とメカニズム
鍼灸の効果とメカニズム 東洋医学から診る5つの体質タイプ
東洋医学から診る5つの体質タイプ 東洋医学とは?東洋医学と西洋医学の違いについて
東洋医学とは?東洋医学と西洋医学の違いについて 鍼灸師×エステティシャン
鍼灸師×エステティシャン 鍼灸師×アロマセラピスト
鍼灸師×アロマセラピスト 鍼灸師×栄養士
鍼灸師×栄養士 知っておきたい鍼灸師のメリットとデメリット
知っておきたい鍼灸師のメリットとデメリット 鍼灸師が使う道具について
鍼灸師が使う道具について 鍼灸師に関連する団体
鍼灸師に関連する団体 鍼灸師としてUターン就職・Iターン就職はできる?
鍼灸師としてUターン就職・Iターン就職はできる? 鍼灸師の就職先
鍼灸師の就職先 鍼灸師の養成施設とは?夜間はある?
鍼灸師の養成施設とは?夜間はある?